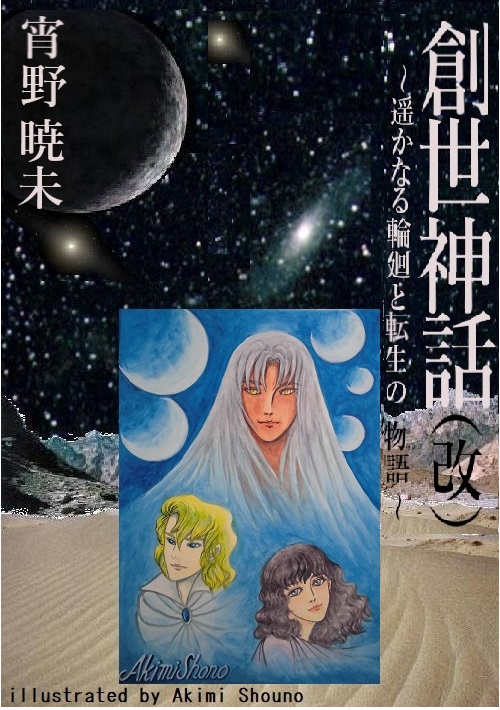8 円形闘技場=COROSIAW
海は、ストーレの降る時間帯には荒れて大波がうねり、憲兵隊の水上艦でさえも航行が難しいことがあるというが、良く晴れて眩しいほどの月光に照らされ、驚くほどに静かだった。細波は月光を反射して煌めき、大小幾つもの月の輝きと、その明るさに紛れる星の瞬きが、彼方の空を美しく彩っている。
しかし、この美しい航路の先に待ち受けるものは、ロウギ・セトにとっても、トルキルにとっても、平穏とは真逆のものであるに違いなかった。
不気味な黒雲に覆われた赤い島に向かって、憲兵隊の水上艦は速度を速める。曳航されるトルキル家の水上船は、抗うこともできずに付いていくのみ。
水上艦は、島のウルクストリアに面した側ではなく、回り込んで反対側の港に向かった。港のそばには、頑丈な石造りの壁が円形状にそそり立っている。円形闘技場=COROSIAWである。
切り立った崖の近くに作られた岸壁に着くと、トルキル家の水上船に、憲兵達が荒々しく乗り込んできた。ロウギ・セトは後ろ手に縛られ、トルキルも、
ロウギ・セトとトルキル、そしてダムセル・ダオルが憲兵達に囲まれる形で下船すると、トルキル家の水上船はゆっくりと岸壁を離れ、やや沖に出て投錨した。船内に留まった憲兵の指図によるものと思われた。
岸壁に二人の男が待っていた。一人は憲兵隊の制服を着ているが、もう一人はウルク人ではなさそうで、黒みがかった肌色に青みがかった髪が頭頂部にだけわずかに生えた小男だった。
「今回の件を任された第五憲兵隊ジグドル・ダザルだ。こっちの男は、円形闘技場=COROSIAWを取り仕切っている、通称“
“蝙蝠”が、へへと笑いながら、トルキルとダムセル・ダオルに仮面を差し出し、ジグドル・ダザルが説明を加えた。
「トルキル大連殿とダムセル殿には仮面で顔を隠していただこう。それが、この円形闘技場=COROSIAWの観覧者のきまりらしい。他の貴族豪族の方々は、すでに観覧席で今や遅しと待っておいでとか」
「いや、観覧に来たわけではないし、そのような趣味は無い。遠慮しよう」
トルキルは、差し出された仮面を受け取らずに言った。ダムセル・ダオルも主人に従い、手を出さない。
「そこのロウギ・セトなる男が出場するというのに、よろしいので? 仮面を付ければ何処の誰とも知られぬのだから遠慮は無用。特別席を準備してあると聞くゆえ、部下に案内させよう」
第五憲兵隊ジグドル・ダザルは、トルキルとダムセル・ダオルに向けてそう言った後、今度は部下に向かって言った。
「そこなロウギ・セトなる男は“蝙蝠”が連れて行くが、念のため、何人か着いて行け。まあ、クリュス島では逃げても無駄。大人しく着いていくしかないだろうがな」
ジグドル・ダザルは、あざけるように笑った。
後ろ手に縛られたロウギ・セトの綱を“蝙蝠”が握り、憲兵達がそれを囲んで、ロウギ・セトは家畜のように引かれて行った。
トルキルとダムセル・ダオルは、仕方なく仮面を付け、憲兵隊に伴われて歩き、円形闘技場=COROSIAWの門をくぐった。円形闘技場=COROSIAWの中に入ると、ジグドル・ダザルの言うように、仮面を付けた大勢の貴族豪族達が、祭りの見世物を楽しむかのように騒ぎ、悪態や罵倒や怒号も飛び交っていた。
わざわざ
クリュス島は、通常ならば憲兵隊が立ち寄ることも無い場所である。鍛冶場で労働するために連れて来られた炎人と、円形闘技場=COROSIAWでの見世物のために連れて来られた罪人と、それらを管理する無頼者達、それ以外は闘技を楽しもうと身を隠して遥々やってくる者達だけ。
ウルクストリアに存在する治安も秩序も、ここクリュス島では期待できず、何があっても闇から闇に葬り去られるだろう。だからこそ、ロウギ・セトを口実にして自分は連れて来られたのだと、トルキルは思った。テムルル・テイグが、政敵である自分を消そうとしているに違いないと。
トルキルとダムセル・ダオルが案内された
真向いにある桟敷席はひときわ豪華で、まるで玉座のような立派な椅子があり、やはり仮面を付けた男が踏ん反り返っているのが見えた。その左右には巨漢の無頼者が立ち、足元には女たちが、酒や料理を持って侍っているようだ。無頼者達の首領の席と思われた。
「ダムセル、炎人や海人について何か知っておるか?」
トルキルが小声で尋ねた。
「目にしたことだけならございますが、詳しい事は存じませぬ。体は我々よりも遥かに大きく、その昔、禁断の秘術によって生み出されたとか。そのような者と闘って、ロウギ・セトに勝ち目はございましょうか?」
「難しいかもしれぬ。だが、今のところ我々には、ここで見守ることくらいしか出来ぬようだ」
「炎人や海人は言葉を解しないと聞きますが」
「せめて話が通じる相手なら……。しかし、いずれにしろ死闘など見たくないものだが」
やがて、場内が一段と騒がしくなった。
円形闘技場=COROSIAWの中央に、小山のような大男が引き出されてきた。緑色の肌に赤い髪の、体中に傷跡のある、怪物のような男である。
「ご観覧の紳士淑女の皆様、さあご覧あれ! 炎人と海人の混血にして、殺戮の蛮人、その名も殺人鬼バルカン! これまでの犠牲者は数え切れず。鋼のような肉体は剣も槍も跳ね返し、その怪力でどんな対戦相手をも捻りつぶしてきた無敵の悪魔なり!」
「さて、対しまするは~」
行司は、もったいぶるように言葉を切った。
「さて、紳士淑女の皆様は、どのような対戦相手をお望みでしょうや。バルカンに負けず劣らずの巨漢の悪党か、はたまた、善良なる市民を幻惑で罪へと陥れる妖艶なる魔女か、どちらも見たい! しかし、紳士淑女の皆様、今宵の相手は、いかなる至高の期待も裏切りますまい。なぜなら、未だかって、この円形闘技場=COROSIAWの対戦相手となり得なかった人物だからです」
行司の長すぎる前置きに、あちこちから野次が飛ぶ。
「お待たせしました。それでは登場してもらいましょう。
もはや行司の声も聞き取れないほどの観覧席の喧噪。
そして、バルカンが引き出された側とは反対側の鉄格子が開き、普段着のままのロウギ・セトが現れた。ロウギは、取り乱した様子もなく、落ち着いた足取りで巨体のバルカンの前に進んでいく。
桟敷席から息を呑んで見守るトルキルとダムセル・ダオル。
視線に気付いたのか、ロウギ・セトが二人の方を見た。そして、何も心配は無いと言うように、穏やかな笑みを返したのだった。
「勝ち目があるのでしょうか?」
ダムセルの問いに、トルキルもはっきりと答えられるはずもない。
「ロウギ・セトが、その言葉通りに異世界から来たのであれば、行司の言う通り、確かに何か策を持っているかもしれぬな」
殺人鬼バルカンとロウギ・セトは、間合いを取って向かい合った。
合図の鐘が鳴った。
「さあ、始まりました。制限時間も反則規定もない死闘です。両者とも武器は携行しておりませんが、ご観覧の皆様よりの善意を妨げるものではありません。ごひいきの側にお力添えなさるのは自由。もっとも、バルカンはその鋼の肉体と怪力こそがすでに武器。ほかのどのような武器も必要ではないかもしれません。対するロウギ・セト。全くの未知数であります。強いのか弱いのか、もし万が一その言葉通りに異世界からの訪問者であったとしたら、我々エラーラ人には計り知れぬ力を隠しているやもしれません。さあ、どうでしょうか。両者、なかなか動きません」
ロウギ・セトは考えていた。
このような目立つ場所で、力を開放するわけにはいかない。
ウルクストリア内については、ほとんどの場所について正確な立体地図をすでに脳内に構築できているし、現在いるクリュス島の場所と、円形闘技場=COROSIAWの場所も把握できている。目くらましを使ってこの場を撹乱し、適当な場所に瞬間移動することも不可能ではない。
しかし、どんな目くらましを使っても、忽然と消えたロウギ・セトには追手がかかるであろう。任務遂行の為には、まだエラーラ内の調査が必要であり、自由な行動が妨げられるのは困る。
全員の記憶を消すという方法もあるが、時間がかかり過ぎ、得策とは言えない。
ロウギ・セトは、対戦相手のバルカンを見上げた。
巨体のバルカンは、ぼんやりと立ちつくし、ほとんど動いていないようだった。目は虚ろで、ロウギの姿を捉えているようには見えない。
「二人とも、何ぼうっと突っ立ってるんだ! 見合いを見に来た訳じゃないぞ!」
「どこが殺人鬼だ! でくの坊じゃないか!」
「金返せ! 金返せ!」
観覧席の貴族豪族達は、口々に喚いていた。
どこからか、何かが投げ込まれ、バルカンの顔に当たった。弾けたそれは、蒸気のような煙のような何かを出す。
バルカンの顔色が変わった。
虚ろだった目には、怒りか憎しみか、激情の炎が燃え、月光のように静かだった肉体は、沸騰するように筋肉が盛り上がり、結ばれていた口が、飢えた獣のように喘ぎ始めた。何かの薬が使われたに違いなかった。
バルカンが猛り声をあげ、大股の一歩でロウギ・セトに拳を振るった。
観覧席が沸き立つ。
ロウギ・セトは、後ろに跳んでバルカンの拳をかわす。
観覧席からは、ロウギが吹っ飛ぶと期待して残念がる声と、いいぞと囃し立てる声。
「バルカン、本気を出せ!」
「ロウギ・セト、逃げてないで反撃しろ!」
バルカンは、巨体にも関わらず機敏だった。身をかわすロウギ・セトを、次の瞬間には追い詰め、両手で掴みかかる。逃げそこなえば、バルカンの握力の餌食となるのは必至だった。
ロウギ・セトの目の前に、細身の剣が投げ込まれた。ロウギが手に取り、鞘から抜くと、切っ先は鋭くとがり、片刃の美しい波紋は、バルカンの鋼の皮膚をも切り裂けるに違いない妖しい光を放っていた。
間髪を置かず、バルカンの目の前にも、大振りな鉾が投げ込まれた。武器など目もくれないかと思われたが、その鉾の両刃の輝きが、バルカンにその鉾を手に取らせたと見えた。
双方が武器を構える。
ロウギ・セトは静かに剣を構え、バルカンは手にした鉾を闇雲に突き立てる。ロウギの剣とバルカンの鉾が激しくぶつかり合い、摩擦の火花が飛んだ。バルカンの鉾はロウギを突き刺そうと責めたが、ロウギは間一髪でかわす。滑らかな舞踏のような動きで右に左に後ろに上にと身をかわすロウギは、手にした剣を舞い飛ぶ蝶の羽ように縦に横に操り、時にその切っ先がバルカンの皮膚を傷付け、
観覧席は興奮の
桟敷席のトルキルとダムセル・ダオルは、冷や汗を流しながら闘技を見守っていたが、ふと気付くと、二人を見張っていたはずの憲兵達が、見張りを忘れて闘技に熱中し、大声を上げていた。
ダムセル・ダオルが、目を動かしてトルキルに何かの合図を送った。トルキルが頷くと、ダムセルは素早く行動に移した。
ロウギ・セトとバルカンの闘技に我を忘れて叫び声を上げている憲兵の背後に忍び寄り、盆の窪に手刀を浴びせて昏倒させると、ようやく気付いて飛びかかってきたもう一人の
「しばらくは起きないはずです」
ダムセルの言葉に、トルキルは頷いた。
観覧席の誰一人として、今起きたことに気付いた者はいないようだった。それほどに、誰もが闘技に熱中し、興奮していたのだ。
いや、気付いた者がいた。
ロウギ・セトが、バルカンとの闘いの最中にありながら、確かにしっかりと、トルキルとダムセルを見たのだ。
トルキルは、自分達が逃げるつもりであることを伝えたいと思った。意図を汲んだロウギ・セトが僅かに頷いたようにトルキルには見えた。
トルキルは、何の疑いもなく、ロウギは一人でも上手くやるに違いないと思った。いや、寧ろ、一人の方が思うままにやれるのではないかと。もともと、テムルル・テイグの目的は自分に間違いないのだ。
トルキルとダムセル・ダオルの二人は、用心深く、桟敷席の外の通路をうかがい、安全を確認して飛び出した。
誰もが闘技に熱狂しているせいか、通路に人影はなかった。とは言え、慣れない場所である。素早く安全に抜け出すのは、容易な事ではない。
戸惑っていると、足早な数人の足音が近づいてきた。
「閣下、そこの物陰へ」
ダムセルが示した垂れ幕の陰に滑り込み、息を殺して身をひそめる。
足音が通り過ぎ、様子をうかがっていると、通り過ぎたはずの足音が駆け戻ってきた。
トルキルとダムセルが身をひそめる垂れ幕が、戻ってきた憲兵達の手にした明かりに照らされた。
「これはこれは、トルキル・デ・ロスル殿にダムセル・ダオル殿、こんな所でお会いするとは」
それは、第五憲兵隊筆頭ジグドル・ダザルだった。
「隊長、テムルル丞相が!」
垂れ幕の奥から、憲兵の叫び声がした。
「死んで……殺されています!」
垂れ幕が開かれ、憲兵達の手にした明かりが奥まで照らすと、頭を血に染めたテムルル・テイグが倒れていた。そばには血の付いた石が落ちている。壁からはがれ落ちた石の欠片と見えた。
「な、なんということだ」
トルキルは、驚きで声を震わせた。
「トルキル殿を捕らえよ」
ジグドル・ダザルが叫んだ。
「待て、我々は何もしていない。奥には行ってもいないぞ」
トルキルは、驚いて叫んだ。
ジグドル・ダザルは、けたけたと笑った。
「それでは、その手に付いた血はなんですかな?」
トルキルが己の手を見やると、確かに血に染まっていた。思わず握りしめていた垂れ幕に血糊がしみ込んでいたのだ。
ロウギ・セトとバルカンの闘いは、まだ続いていた。
幾度となく剣と鉾とが打ち合わさり、体と体もぶつかり合ったが、互いに致命傷を負うことなく、バルカンはロウギに向かって鉾を投げ、ロウギはかわして宙を舞った。
バルカンの様子はおかしかった。その瞳に宿った怒りと憎しみの炎は、ロウギに向けられたものではなかった。荒れ狂うように腕を振り回し、重い鉾を拾っては投げつける。
ロウギはふと思った。もしかしたら、バルカンは自分自身と闘っているのではないかと。
(……殺したくない……この悪夢は生きている限り続く……殺してくれ……)
それは、バルカンの心の内から発せられた思念だった。
(バルカン、お前は、薬漬けにされ、殺人を強いられているのか)
ロウギ・セトは、バルカンに呼び掛けた。しかし、答えはない。薬により自己を失ったバルカンには、思考も判断も失われていた。
バルカンは、獣のように咆哮した。
ロウギ・セトは、自問した。殺すべきか、生かすべきか。
その時だった。
地響きと共に円形闘技場=COROSIAW全体が揺れた。いや、揺れたのはクリュス島全体だった。
観覧席から悲鳴が起こった。
「あれを見ろ!」
鋭い叫び声に人々が顔を上げると、クリュス島を形作る山が火を噴いていた。
大小の火山弾が降り始め、我先に逃げようとする人々。しかし、地響きと揺れはますます激しくなり、歩くどころか立つこともできなかった。
クリュス島の山は、火柱を上げ、白い水蒸気を噴き上げていた。さながら沸き立つ雲を昇る火龍のように、神々しくさえ見えた。火龍は天へと上り、空を黒雲で覆った。
轟音と共に、円形闘技場=COROSIAWが地面ごと真っ二つに割れた。その深い割れ目に、ロウギ・セトはバルカンと共に堕ちていった。