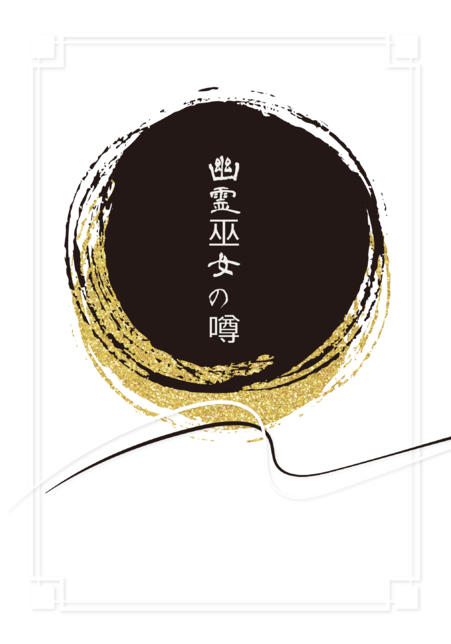9
「二十代になったのだから、カディオにはそろそろ婚約だってしてほしいのよね。わたくしとしては、可愛いし有能だし、シェスティを娘にしたいくらいなのだけれど――」
言いながら、扇越しに王妃の流し目が向いて、シェスティはどきっとする。
貴族たちが耳を済ませるのが見えた。
まずい、そう感じてシェスティはすぐ笑い飛ばすことを決めた。
「いえいえ、私たちはただのライバル同士ですし、誰もが知る犬猿の仲ですよ。あり得ないですよ」
答えたシェスティは、隣でカディオがシャンパングラスを見つめて震えているのに気付いていなかった。
王妃が「ふうん?」と息子の様子を眺めている。
「このような場で、そのような冗談はやめたほうがいいですよ」
「そろそろ我慢の限界だと思うから、この場で言ったのだけれどね。今日ではっきりさせたいのよねぇ」
「はい?」
「あなた、今夜は一緒にうちに泊まっていくでしょう?」
突然そんなことを尋ねられて、シェスティはきょとんとした。
「その予定ではありますよ。また父様たちと夜まで飲み明かすのでしょう?」
この両親たちはかなりお酒が好きだ。よく王宮に泊まっては『この一時は立場から解放されるー! 飲むぞー!』と、学生時代と変わらないノリで飲んでいる。
すると国王が、ニヤニヤしてカディオのほうを見た。
「カディオ、シェスティは美人に育ったからな~。建国祭が落ち着いたら、向こうの国から求婚の知らせがあったりするかもな~?」
シェスティは苦笑した。思わず、顔の前で小さく手を振る。
「いやいや、そんなことはないですよ」
その時、ガシャッと音が聞こえて、口をつぐんだ。
国王と王妃、父と母も同じ方向を見ている。
記憶に間違いがなければカディオがいる場所だが――と思って目を向けたところで、シェスティは考えるよりも先に駆け出していた。
「な、何をしているのよっ」
カディオの手の中で、クラスが握り潰されて粉々になっていた。
慌てて彼の手を開かせる。そこから割れたグラスの残りが床に落ちていく。
王妃に続いて母も指示を出し、使用人たちが必要な道具を抱えて駆け付ける。
「獣人族の怪力を忘れちゃったの? 怪我はっ?」
カディオが我に返ったみたいに、ようやくその金色の獣みたいな目を、シェスティへと移動した。
「あっ、危ないぞシェスティ。触らないでいいから。人族の肌は俺たちより弱い――」
「そんなこと言っていられないでしょっ、怪我は!?」
気圧されたようにカディオがのけぞり「な、ない」と答える。
グラスの破片が残っていたら危ないと言われ、シェスティは父に引き離された。手を洗うための水の入った器を使用人から差し出され、カディオがぶすっとした顔で手を洗う。
「まったく、お騒がせな息子だなぁ」
さすがに困ったのか、国王の頭についているカディオとまったく同じ獣耳が、半ば下がっていた。
「無理そうなら休みさい。シェスティは、私たちと一緒にデリアード公とお喋りに行こうか」
「いらしているのですか?」
「うん。今日の飲み会に参加するよ」
にこーっと笑った国王の表情が、次の瞬間「えぇ」という具合に変化した。
「俺は休みません。シェスティが行くならも、同行します」
いつ復活したのか、カディオがシェスティの隣に立って凛々しい姿勢でそう主張した。
(え、その理由はいったい何?)
彼は、もしや邪魔をしたいのだろうか。
ここまでくると、そんなバカみたいな可能性が頭に浮かんでくる。
(仲良くなるため歩み寄られていると思ったけど、それは私の勘違いで、私、まさか地味な嫌がらせをされているとか?)
そんなシェスティの反応を見て、国王がため息をもらす。
「もうさ、私は諦め気味だよ」
「あなた、この状態の獣人族は、実の親の声も届きませんわ。わたくしたちもそうだったでしょ?」
「厄介な息子だなぁほんと」
そんなこと、実の息子の前で口にしていていいものだろうか。
シェスティは両親と一緒に、なんとも言えず見守ってしまった。
それから国王たちと場所を移動した。その途中で兄が合流し、領地からわざわざ出てきてくれたデリアード公の家族に会った。二人の子供たちはお喋りも上手になっていて、シェスティは微笑ましかった。
ただ――なぜかカディオがまたおかしなことになった。
シェスティが腰をかがめて二人の子息と話していたら、突如ぐんっと身体が浮いた。
「えっ」
国王たちも唖然としていた。
カディオが子供を持ち上げるみたいに、子息たちの前にいたシェスティを後ろから持ち上げて、上へと遠ざけたのだ。
しかも、彼の口から次に飛び出したその理由というのが、また意味不明だ。
「大きくなろうが、君たちにチャンスはない」
子供たちは狐耳をぷるぷると震わせて、まさに蛇に睨まれたカエルのように動けなくなっていた。
彼らの両親がそれぞれ後ろから確保したところで、大泣き。
国王は撤退を決めたのか、素早い動きでカディオの背を押した。王妃がシェスティの両親を引っ張る。
「やー、すまないねデリアード公! ちょっと、息子、今こんな感じでさ!」
国王の逃げ足は速かった。
会場内を彼が走る姿はたびたび見られているので、何人かが「また走ってるぞ」という声は、シェスティの耳にも届いた。
(というか私を、先に降ろして欲しい)
シェスティはカディオに持ち上げられているせいで、見ていく貴族たちの視線を真っ先に受けて口元がひきつっていた。
そのあとは気を取り直したように会場にいる者たちと歓談していくことになったのだが、シェスティはもう心配しかなかった。
カディオはやはり、三年前と違って一切喋ろうとしない。
ただただ、シェスティの隣に大きな態度で立っている。
おかげで話し相手はこちらから若干距離を取り、シェスティは双方の親たちの少し後ろにいる形になっていた。
「……あのね、カディオ? 誰も話しかけられないみたいだから、その態度をどうかできない?」
「俺が、どのような態度だと?」
え、もしかして自覚がないのだろうか?
シェスティは、不機嫌としか思えない彼の横顔を見上げた。
「まったく、父上たちもどうして同年代の婚約者がいない令息がいるところばかり回るんだ……」
腕を組んだカディオの口調は、なんだか苛々しているように聞こえる。
(ほんと、どうしたのかしら。体調がまた悪くなってきたとか?)
シェスティは会場内を見渡しつつ、言う。
「不自然ではないでしょう? 建国祭は、恋愛成就の日とも言われているのよ。まだ縁が結ばれていない子供を連れ回すのはよくあることだわ」
「だから一番警戒しなくてはならない日だ」
「どうして警戒日になるのよ。あっ、ドリンクをください!」
シェスティはお目当ての飲料を配っている者を見つけ、こっちよと手を振る。
「そういえば、毎年カディオ不機嫌になっていたわね」
「俺がなかなか口にできないのに、行動が起こせるやつが憎たらしくなる……今の俺が情けなさ過ぎるのも自覚しているのに、くそっ、本能が……っ」
急にカディオが額を手に押し付ける。
「大丈夫? 今年はすごく体調が悪そうだものね。はい、飲み物をどうぞ」
ちらりと見てきたカディオが「うっ」と顔を顰める。そして、逡巡の間を置き、大きく息を吐いた。
「……シェスティ、今の俺にワインはまずい」
「気つけで飲んでいたじゃない。頭痛にも効くって」
「いや、これは頭痛では……」
すると国王が肩越しに振り返り、ニヤリとした。
カディオのこめがみに小さく青筋が立つ。
「ほぉ、シェスティが差し出したワインが飲めないのか? これなら私がもらっちゃお――ふげっ」
あろうことかカディオが、やってきた国王の左頬を手で押して、ワイングラスを右手で彼から引き離した。