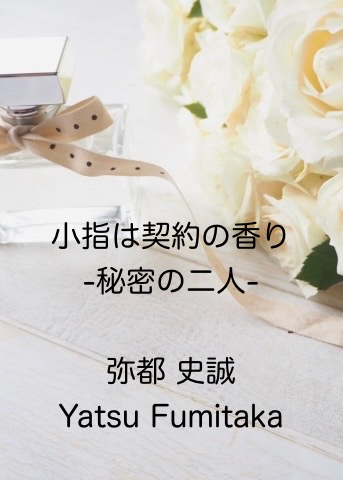『記憶』#1
翌日の授業後。
ロイスはクラス全員から回収した、プリント用紙を入れた封筒を小脇に抱えて、シエンの元へ向かっていた。
護衛に付けているロドルフは、「あとは渡して、迎えが来るだけだから」と、部活に行かせた。
「……はぁ」
もう何度目か判らない溜め息を吐く。
職員室にシエンはおらず、教師に与えられた個室にいるのではないか、と教えて貰った。だが、個室は何十人といる教師全てに与えられている為、探すだけでも一苦労だ。
やっと見つけたシエンの個室。
その引き戸の前に立ち止まり、目を閉じて、大きく深呼吸をして、高鳴る心臓を落ち着かせる。
背後の窓から夕陽が差し込み、夕暮れが近いと知らせる。
あまり遅くなると、送迎してくれている運転手が心配するだろう。
ロイスは再度小さく深呼吸して、覚悟を決める。
学長の息子として、生徒会長としての威厳ある、“いつもの自分”でいれば良いだけではないか。
勇気を出して扉をノックして、小さく咳払いをする。
「二年一組のロイス・リチャードソンです」
「はい、どうぞ」
シエンの声だ。一瞬、身体が震える。
「失礼します」
扉を開けると、シエンはデスクワークをしていた。他のクラスの復習プリントの採点をしているのだろう。
一歩踏み出して、室内に入る。廊下の冷たく無機質な空間とは違い、香《こう》かアロマのような、微かに甘い香りがする。
とうとうシエンの領域に入ってしまった。
シエンまでの距離、およそ五歩。
「──復習プリントを持って来ました」
シエンは採点のペンに蓋をして、ロイスの方へ椅子を回転させる。
「お待ちしていましたよ、ロイス様」
「…え?」
ロイスは小さく声を上げて、瞬《まばた》きを二回した。
シエンのセピア色の目が懐かしそうに笑みを浮かべて、こちらを見ている。
「お久し振りです」
すぐに返事が出来なかった。
初等部の頃は、夏休みや冬休み、そして春がやって来る度に「シエンは戻って来ないのか」と、屋敷中の使用人に聞いて回った。
「……シエ…ン」
覚えていてくれたのが嬉しかったのか、名を呼ばれたのが嬉しかったのか、待っていてくれたことに驚いたのか、突然居なくなったことに物申したいのか、とにかく色々な感情が混じった涙が出そうになるのをグッと堪える。
「大きくなりましたね」
シエンの子供扱いするような言葉に、一気に教師と生徒の関係から、雇い主の息子とその執事の息子の関係に戻ってしまう。
「あ…当たり前だ! あれから…何年経ったと思ってるんだ!」
本当は、こんなこと言うはずでは無かったのに。
素直になれなくて、自己嫌悪に陥る。
「それはそうですね。私の中で…」
焦りから、シエンの言葉を遮ってしまう。
「これ、人数分入ってるから。ちゃんと届けたからな」
ロイスはシエンの目を見るのが怖くて、視線を逸らして、プリント用紙の入った封筒を差し出す。
ゆっくりと立ち上がったシエンが前に立つと、ロイスの身体が熱くなり、背中に嫌な汗が出て来る。
「ありがとうございます」
シエンが腕を伸ばすと、優しく包み込むような甘いバニラのような香りがして来た。アイスクリームより遥かに濃いけれど、どこかスッキリとした香りだ。
(昨日とは違う香りだ…)
ロイスの差し出した封筒を受け取ろうとすると、シエンの成熟した大人の男の指が僅かに触れる。
「……‼︎」
驚いて視線が向き、無意識に指がビクリと動いて、その手を慌てて引っ込める。
ロイスが微動だにせずにいるのに気付いたシエンは、彼が緊張していると勘付く。
「よろしければ、お茶でもいかがですか? 学校の話も聞きたいですし」
「え、お茶…」
シエンは、目を泳がせて挙動不審のロイスがおかしくて仕方ない。入学式の時は、生徒会長として、あんなに堂々としていたのに。
ロイスはすぐに出ようと思っていたのだか、思いとどまる。
「──少し、だけなら…」
「それは良かったです」
シエンは微笑むと、ロイスから受け取った封筒をデスクに置く。
「──ご用意しますから、そこの作業机で申し訳ありませんが、お待ち下さい」
シエンの言う作業机とは、二台並べてある長机のことらしい。
ロイスはぎこちない動作で机にスクールバッグを置くと、ゆっくりと備え付けのパイプ椅子に腰掛ける。
奥の給湯室から食器の音がする。
ロイスはシエンの個室を、ぐるりと見渡す。
他の教師は私物を持ち込んで、それぞれの個性を出しているが、新任の為か必要最低限の物しか無い。資料を入れる書棚も、ほぼ埋まっていない。良く言えばシンプル、悪く言えば殺風景な部屋だった。
でも、それがまたシエンらしいとも思った。
ただ、壁に貼り付けてある、一見すると古地図のような茶色の世界地図が印象的で、所々不規則に赤色と青色でチェックが入っていた。
奥の給湯室から湯が沸く音がして、食器のを扱う甲高い音がする。
待っている間に、いくらか緊張が解けていた。
「──お待たせしました」
その部屋の主《あるじ》が、両手にマグカップを持って現れた。
「──まだ紅茶はご用意が無くて申し訳ありません。私の家の出身地のお茶です。お口に合えば良いのですが」
そう言ってロイスの目の色に似た、鮮やかな青色のマグカップを差し出されると、また先程の甘い焼き菓子のような香りがして来る。
(今日は、この香りの香水付けていたんだ)
昨日は自分の好きな紅茶の香りがする香水を付けていたのに、今日は違う香りがする。
それだけでシエンとの距離が離れてしまった気がした。
マグカップを両手で受け取ると、中には紅茶に似た色の液体が入っている。
まだ湯気が立っている為、フーフーして飲める温度まで冷ましていると、お茶本来の、ほんのり甘い香りが鼻腔をくすぐる。
向かいに座ったシエンからは、コーヒーの香ばしい大人の香りがした。
シエンから香る穏やかな甘い香り、異文化のお茶とコーヒーの香りがロイスを完全にリラックスさせる。
未知の味と熱さに、恐る恐るカップに口を付ける。
「…あっつ」
「相変わらず猫舌なんですね。気を付けて下さいよ」
シエンもカップに口を付けながら、クスクスと笑った。
「う…うるさい」
再度フーフーとカップの中に息を吹きかけながら、チラリとシエンを盗み見る。
シエンが片肘で頬杖を付いて、こちらを見ていた。
慌ててカップの中に視線を移し、まだ僅かに湯気の残る茶色の液体を、少しだけ口に入れてみる。
少し苦味の効いた、飲んだことのないお茶だ。舌触りに渋味が残り、ややザラつきもあるが、奥行きも感じる。
「──少しクセはあるが悪くないな」
香ばしさと花のような匂いが、僅かに鼻を抜けた。
遥か遠い、シエンのルーツである北西圏。その距離と歴史も思わせる味だった。
飲める温度まで冷ましながら、三分の一ほど一気に飲んだ。
自分では気付かなかったが、かなり喉が渇いていたようだ。
「──で、今まで何処で何していたんだよ」
両手でカップを包み込んで、中のお茶の水面に映る自分の顔をぼんやりと見つめながら、ロイスはぽつりと呟くようにシエンに問う。
「大学は先祖が住んでいた北西圏のベイチェン大に行きました。在学中は長期休暇を利用して世界中あちこちに行きましたよ」
「へー」
自分の世界は、ミレニア・シティーとリチャードソン家所有の別荘地くらいのロイスは、シエンの言葉に興味深々になる。
「お金はありませんから、長距離を歩いたり、ヒッチハイクをしたり、現地の人の家に泊めて貰ったり、なかなか楽しかったですよ」
危ない目にも遭ったが、それは黙っていた。
「──私が地理を専攻したのも、それがきっかけですね。草原が地平線まで広がっている国もあれば、巨大な湖と共に生活する人々もいる。山ばかりの国もありますしね。その種々多様さが私をこの“道”に進ませたのかもしれません」
シエンは思い出を懐かしむように微笑んだ。
「やりたい事って…世界旅行だったのか」
お茶に視線を落としたまま、ロイスは納得したように呟く。
「……それは…おまけ、みたいな…物ですね」
ここで初めてシエンが言い淀む。
「何だよ、それ」
ロイスは顔を上げてシエンを見ると、今度はシエンが横向きに座り直してしまった。