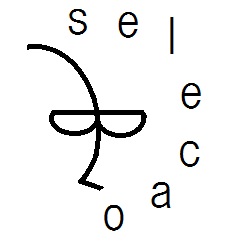1 たまの事
「本当に、僕がここに住めるんですか?」
聞いていた年よりも幼げに見える少年はそう呟いて、遠目に映るその屋敷に猫のような大きな目を見開いて固まってしまった。
その白でコーティングされた木の柵に囲まれた広い敷地の中、そびえ立つ建物が自分の相続した家だなどとは、ハッキリと言葉にされるまではまさか夢にも思わなかったのだろう。
この敷地に出入りするための、観音開きのゲートを通過するだけでも腰が引けていた少年だ。
自分にもたらされた物の思いがけない大きさを前にその声が震えていたのは、彼の生い立ちから考えても仕方のない事ではある。
おそらく実際に屋敷を目にするまでは、敷地の隅に建てられた物置のようにこじんまりした小屋でも想像していたのではないだろうか。
「柵から内側は全部、玉生君の物だという手続きはこの間のサインで済んでいるからな。遺言でも、“ちゃんと本人が住む事”という条件だったろう?」
「はい。はい、あのー……まさかこんな立派な建物だとは、思ってなくて―――」
和平三十三年、日の本の国とも称される、大大和帝国。
全国の神社仏閣を帝の血統の一門が御幸し、その地で執り行う儀式によって保たれる結界にて列島ごとを囲い、現在は鎖国状態にある国である。
例外は、海中に建立した鳥居に帝が祈祷する事により無人の小島や海沿い近隣の埋立地へと海路を開き、諸外国との貿易のためのいわゆる出島を作っての対応だ。
その輸入品を扱う貿易商人の中には、華族としての地位を得る者もいれば大枚をはたいて二束三文の品にしてしまう者もいて、目利きでなければ運次第といった面が大きいため山師のうちに数えられていたりもするのだ。
空路の方も神風と呼ばれる強い風が作る壁が日本上空への侵入を遮断し、外界からの干渉を防いでいる。
国内の空ならば神風が吹くよりも低い空域を飛ぶ、回転するプロペラを持つ回転翼機という特徴そのままの名の飛行機の存在はあるが、基本的に国や都市で緊急時に一直線に対応できる機体として配備されているものであって、民間での所持はなかなかにハードルが高い。
それに地上の移動も、都市ごとに交通網が構築されて公共の電車やバス利用が推奨されており、隣の県へ行くにも国を横断する列車に乗るのが一般的だ。
ただしその列車も往路と復路の二車線は絶対的な本数が少なく、日常で県を跨いだ移動をするのはそう楽な事ではない。
それ以外にも時間がある者は長距離バス、地位や金で公用車や自家用車を持つという選択肢もあるにはあるが、訳あってそれもあまり一般的ではなく気軽に利用できるものではない。
それでも儀式の関係から帝の御所を中心とした発展をとげたのが、東の首都である江都と西の首都である京都である。
つまり、大和国は東都と西京を中心とした二都制なのである。
そして古くから神へ捧げる祭りが各地で行われ、八百万の神を讃えるゆえか実りも豊かなので、生きるに必要な物は足りて土地に根付く国民性だ。
おまけに古くから市民にも絡繰・戯画などの文化、食に対する追求などの一人遊びが好きな民族性でもあり、その華やかな文化は知る人ぞ知るという独自性を持って噂に聞いた外の国の人々を「不思議の国」として驚嘆させている。
その大和国に住む蔵持玉生は、理由あって孤児院で育った子供であった。
今現在、父親の所在はハッキリしないが、母親の方はつい最近まで健在であったにも関わらず院にあずけられていたのは、彼女の性質からして当然の成り行きのようなものだった。
その母親である蔵持玉子はまだ少女の頃、突然の両親の死によって弟の宝と共に親戚の家にあずけられたが、そこではあまり歓迎されなかったのだという。
それでも当初、姉弟は二人で励ましあってそこですごしていたのだそうだ。
ところがある日、その弟がどこかへと忽然と消えてしまい、親戚の方は放置気味だったとはいえ痛くもない腹を探られ、以後の玉子の扱いは疫病神としてより粗雑になっていった。
その結果、玉子は何も満たされないガリガリの少女に育っていったのだという。
義務教育と共に保護者としての義務も終わり、玉子が働ける年になると「早く出て行け」とは言われたが、仕送りをせびるでもないだけ悪辣ではない普通の人たちだったと、そんな風に玉子は語っていた。
もっとも後に傍野から聞いた話では、彼ら曰く「玉子の稼ぐの端金」と万が一彼女が問題を起こした時のリスクとを天秤に掛けて縁切りしただけだろうという見解の様だが。
今回の玉子の訃報で件の親族と顔を合わせる機会があった傍野は、宝本人からも人間性については言及されていた上に彼の遺産絡みの問題で「碌でもない」と判断したらしく、玉生にも会おうなんて気は起こすべきではないとクドい位に言い聞かされた。
ちなみにそこそこ小金持ちで、遠縁の親族の資産の情報が自然と耳に入るほどの力もあるので、余計に倉持姉弟への仕打ちが許し難いのだそうだ。
まあ、それはとにかくその後は玉子も自活するようになり、人並みの食事で人並みの女の子になり、一緒にいてくれる人ができると寂しくなくなったと息子に微笑んで見せた。
「そんな時にあなたのお父さんと出会って、いつか奥さんにしてくれる約束をしてくれたけど、あの人はお金で困ってどこかへいなくなってしまったの」
彼女はそんな事を、男と別れて次の男ができる間の寂しい時期に、よく息子の玉生に話したものだった。
それは今になって思い返しても別に恨み言などではなく、単に自分の事を誰かに話したかっただけだったように思える。
移り気なわけでもないのに生涯に渡って男を渡り歩く事になった原因も、自分が相対する者に気を回せないその人としての稚さにあり、息子に対してもそれは終生変わらなかったのだ。
そんなある日、最近家にいる男の妻だという女性が訪ねて来て、その話の中で自分の名前が出たのを玉生は扉の影からドキドキしながら聞いていた。
「私にも生活があるから慰謝料は貰うわ。それとよけいなお世話かもしれないけど、子供の世話ができないのなら孤児院にでもあずけなさいな」
彼女の常識に加えて、万が一荒んだ生活の果てに虐待などしでかして最悪の事態にでもなってしまったら……そんな父親の子供というレッテルを、なんの落ち度もない我が子に貼られてしまう危険性を憂慮したのだろう。
それからしばらくは、今日明日にでも母親に捨てられてしまうのではないかと玉生は恐れたものだった。
今にして思えば、彼女は男がいるとほかの事はすっかり頭から抜けてしまう、そんな女だったのだろう。
一人で放置されている間に飢えて死ななかったのは、おそらく運が良かったのだろうと玉生は思っている。
母親の付き合う男の中にも、訪ねて来る時に菓子などの日持ちがする食べ物を差し入れてくれる気の利いたタイプがいたり、少しの小銭を気まぐれに握らせてくれたりする者もいてそれでどうにか食いつないだりもした。
それに忙しくて構えないという理由から別れる事になった人物が、玉生を既知である近所の独居老人の家に紹介し、話し相手とお手伝いで少しの手間賃を貰えるように話をつけてくれたのも、これ以後の生活に大きく影響している。
後に子供の養育能力に欠けるという国の判断に、自覚のあった母親が素直に応じて孤児院に引き取られた先での玉生の生活は、それまでに比べたらいっそ穏やかで滞りなく過ぎていった。
そこは国が主導する施設であり、玉生の担当は務めるどの子供も当たり障りなく平等に扱うある意味模範的な公務員だったので、たびたび起こる執着する偏愛による揉め事とも無縁であったのも幸いであった。
その当時の玉生の最も深刻な問題は食事を横取りする悪ガキの存在だったが、子供の好きな物から半分だけ先に譲るという手段でやり過ごせば元々うっかり子供の食事を忘れる母親のせいで少食だった事もあり、毎回の食事の量が少ないくらいはそう大した問題でもなかった。
母親本人からして自分の食事を忘れがちでそれが普通で育ったものだから、そもそも親子でその深刻さが分かっていなかったのである。
それでも、傷んだ物を食べさせたらお腹を壊すので気を付ける位の愛情は確かにあったのだ。
おかげで彼の味覚は正常であり、今では美味しい物を食べる喜びも知っている。
そうやって過ごすうち、生い立ちからの諸々に左右されず蔵持玉生その人を認める気の合う友人も何人かできて、母親に選ばれなかった子供はそれなりにそれらしく生きていた。
ただ、十四歳の玉生はもうすぐ小学校高等科を終える。
義務教育は小学校通常科の六年間であり、さらに二年間を高等科に通ったので孤児としてはすでに恵まれた経歴とも言える。
それというのも通常科卒業の折に当時の院に多大な寄付金が入った事で、学力のある希望者はさらに進学を許されたという幸運の賜物なのだ。
噂によると、同期の院生の身内がわけあって個人を特定されないように全員をその進学希望の対象にしたのだろうという話だが、玉生は今でもその誰かと身内に感謝している。
とはいえ今の状況なら、もう少しアルバイトを増やして貯金をしながらさらに一年高等予科に通い、その上の進学先である高等学校へと進むのも可能であり、彼の友人たちは玉生に強くそれを勧めている。
でも――と玉生は躊躇う。
彼のいる孤児院は、曲がりなりにも国中から人の集う東の都である江都のすぐ隣、都町の中心部にあるのだ。
都町といえば大和国における商業都市東の雄であり、西の最大商業都市である大坂と対をなす。
そんな都会では人が多ければ多いほどに喜怒哀楽に悲喜こもごもがあり、サクセスストーリーを手にする人の裏で夢破れ失意のうち力尽きる者がいる。
それが集団の要の者なら自分の身を守れるわけもない幼い者達も道連れだ。
叶うならそういった無念の境遇に生まれついた子供達をできるだけ多く院に受け入れ、例え束の間の安寧であっても恵まれた生活を味あわせたいと心ある関係者ならば願っているだろう。
つまり院生として学生のうちは孤児院に留まるのは可能だが、玉生がいなくなればその空いた場所に入れる者がいるのだ。
だから新たに住む場所を探し生活を始めるなら、進学などしている余裕はなくなるだろうが、そろそろ別の誰かと代わるため院を出てもいい頃だと玉生はここしばらくずっと考えているのだ。
院の出身で希望者は、職業訓練施設で適職を調べてから本人に合ったその道へと補助と寝食の場を提供してもらえる。
ただし国営で全国に点在しているのでどこの県の施設の所属になるかは不明で、首都である江都や都町などは常に定員がいっぱいなので、おそらくこの地を離れる事になるだろう。
そして国の機関ゆえ、そのままその地に就職となる形式が一般的にできあがっているというもっぱらの噂である。
つまり、地方に行くとなると友人たちとも滅多に――もしくはもう二度と会えなくなるだろうと予想ができる。
その様な事情もあり、親しい友人の保護者に援助の声などかけてもらうとつい進学へと心が揺れてしまうのだが、普段から何かと玉生を気にかけてくれるその優しさにそこまで甘えていいものかと二の足を踏んでしまうのだ。
その好意をありがたいとは思いながらも、実の親元を離れてから孤児院暮らしの玉生にとって、他人に甘えるのはあまりにもハードルが高すぎた。
もう長い間顔も見ていない母親の訃報が玉生の元に知らされたのはそんな時だった。
それと共に彼女の語った思い出の中でしか知らない叔父から、彼女の産んだ子供へ限っての遺産譲渡を託されて来たのだという人物からの知らせも届いた。
行方知らずだったという叔父がその後どうしていたのか、母親はそれを知っていたのかと玉生には疑問ばかりだが「自分もそう詳しくはないが……」と親族との確執とそれに連なる理由から叔父は表に出たがらなかったと、彼の使いの口からは聞いた。
その使いは傍野捜と名乗り、叔父である蔵持宝とは学生の頃から付き合いがある現在の生業は“何でも屋”で、叔父はその得意先だったのだそうだ。
初対面で「行方不明になる前、顔だけは知っていた少年時代の奴の姿に君はよく似ている」と言ってしばらくマジマジと玉生を見て、「たしかに似てるのに、表情のせいで妙にカワイイのがオカシイ」と評されたのが、むしろ普段「淡々としたかわいくない子供」と言われがちな身には解せなかった。
そして遺産譲渡の書類にサインをしたその日から数日後、改めて傍野から孤児院に連絡があった。
引き継ぐ家屋の場所を教えるために直接現地へ案内するという話しで、できるだけ早いうちに孤児院の場所を次の子に譲りたいという玉生の希望を聞いていたので、全ての手続きが済んで早々に声をかけてきたのだという。
詳しい場所を聞くと相続する家があるのは、現在の利用駅である都内の内側を廻る小江都線ではなく外周の大江都線側ではあるが、バスでの乗り換えの手間に慣れれば今の生活圏からも近いのだそうだ。
それで玉生が、これからバイトまでの半日は時間が空いていると言うと、傍野はすぐに孤児院の近所まで商用車のキャラバンに乗って迎えに来た。
出先で公衆の自働電話からの連絡だったのでそのままこちらへと来たらしく、助手席にも置かれた荷物を移動させる傍野の横から見えた車内は、物置をそのまま移動させているかの様な状態だった。
傍野曰く探偵はフットワークが大事だと、後部にはカメラやあちこちの地図・テープレコーダー・懐中電灯・傘・変装用の衣装など様々な道具が積まれている。
なんでも咄嗟の事に対応するために必要な物を持ち歩いているのだとかで、よく見るとカバーの掛かった二輪車らしい物まである。
人によっては「いいから整理しろ」と一蹴されそうだが、素直な玉生は単純に『大変だなあ』と納得して、空いた座席に収まった。
遠出の時や帰宅が遅い時間になるとちょっと過保護な友人が家の車を出してくれるので、車自体には乗り慣れている玉生なのだが、傍野の愛車は車高が高く助手席に座るにもステップを上るのが目新しい。
ちょこんと収まった座席からの高い視界は、目に映る近所も普段とは違って見える。
そんな車窓に流れるいつもなら見入ってしまう景色にも上の空なのは、これから行く先への期待と不安が大き過ぎるせいだろう。
そんな無口になった玉生に、傍野は「いい機会だし、やっぱり玉生君も知りたいだろうから」と彼の知っている事情を少し語ってくれた。
「奴は君のお姉さんとどうしても相容れない所があってさ」
「君のお母さんは奴が援助しても計画的に使うって事ができなくて、あればよけいに悪い相手が寄って来るというか」
そういう相手は不思議とすぐに消えたが、玉生にも何人か心当たりはある。
「まあ、とにかく知れば色々と言いたくなるしで言い合いになるのも嫌になっている時に、しばらく抜けられない用事で遠出をして戻ったら玉生君が産まれていたらしくて、対応を悩んでいるうちに孤児院で落ち着いていたんだよね」
「奴は君を引き取るには問題のある場所を飛び回って定住もしてなかったし――あ、いや、家はあったけど必要な保護者の方がね、留守じゃ意味ないからさ。孤児院に寄付をして環境をある程度整える事で自分を納得させてたってわけなんだよ」
どうやら玉生の高等科進学の際に寄付があったのはそれらしい。
「それに君が幼いうちは、何か価値のある物を相続したと聞きつけた途端に飛んで来る、血縁の義務も義理も果たさないのに権利だけは主張する輩が、名ばかりの保護を買って出る可能性が高かったからね。奴はその理不尽な存在を君には関わらせたくなかったから、自己判断が認められる年までは譲渡を待っていたんだ」
実のところおそらくは伝えるタイミングを図っていた傍野から、そんな風にポツポツと会わず終いの叔父とその姉である母についての話が聞けた。
もうとっくに諦めていた母親でもやはり訃報はショックだったが、叔父の事では知らない所で自分を気にかける人がいてくれたという事実に、孤児として育った身の上ゆえに常に凍える部分を持つ玉生の心はほんのりと暖められた。
ついでにあの話たがりの母親が、叔父の行方不明後の近況についてほとんど口にしなかったのは、どうしても小言を言われる自分の姿を省いて語れなかったせいなんだろうな、と内心では苦笑してしまったのだが。
「……一度くらいは、会ってみたかったです……」
しょんぼりとした小さな呟きが耳に届いた傍野は、”ここにはいない”相手に向かって『いつか会ってやれよ』と密かに苦言を念じてやった。
そして今、玉生は緑が多く広場と呼ぶべき開けた土地で、公共の施設に使用する規模の屋敷を遠目に見ている。
慣れるまでは住人ですら屋敷内で迷いそうな広さなどとは思いもよらなかった彼は、頭が真っ白になり途方に暮れていた。
今日は軽く覗いて、できれば手を入れなくてはならない場所の見当を付けておきたいなどと何となく計画していただけで、実際は未だ遺産の譲渡についてもふわふわとした夢の中の出来事のように感じていたのがこれでは……
柵の内側から藁色の天然石でできたアプローチが、芝生を突っ切り家へと招くかの様に敷かれているのだが、招かれている玉生の方はその一歩が踏み出せないでいた。
「で、どうする? 用事ができた蔵持がうちの事務所に来るのがいつものパターンだったから、俺も正直ここの案内ができる程には詳しくないんだが」
とりあえず想像もしていなかった規模の建物を自分が相続する家だと言われ、どう考えても予定していた時間内ではロクに中を見られないと悟った玉生は、「造りはしっかりしているし、最近一通り見て回った奴が問題ないと言ってたぜ?」との言葉を傍野から聞いて、内見はあえて先延ばしにすることで心の準備をしようとの結論に至った。
しかし、引っ越す際は家の周囲の環境を確認するのがポイントだという傍野の勧めもあり、せっかく現地まで来たので手前側に広がるシロツメ草の上を家の方に向かっておっかなびっくり歩いてみるのだった。
「ほら、あの辺の木は多分ナッツ系の木で、あっちの方にはでっかい桜がある。春には花見ができるぞ」
その言葉に目を丸くした玉生は、傍野が指を指した先を見て「わぁ……」と頬を上気させた。
「ちょっとは楽しみになってきたろ? まあ、ここが広くて困ってるなら友人でも誘ってみるのもいいだろうしな」
当然ながら傍野は直接に後見人として指名されたからには、玉生が誘いそうな仲のいい友人についてはある程度調べて依頼人に報告した上で、問題ないと許可が下りているからこそお気楽に共同生活などを勧めているのは言うまでもない。
見ようによっては思考誘導をしているとも取れるが、このままでは脳内でパニック状態の玉生がいつまでたっても落ち着かない可能性がある。
あの家の事も、万が一"恐怖”の方で玉生のイメージが固定してしまっては、存在を拒否してしまうかもしれない。
先に特異性を教えられたらいいのだが、口にしようとした時点で家の事は傍野の記憶から消去されてしまうのだ。
しかも今あの家は、持ち主になった玉生の信用している人間以外は出入りを"許さない”と思われるので、直に案内して仲介をしようにも会ったばかりの傍野ではおそらく信頼度が足りない。
挑戦してみて家に叩き出される姿を見せては玉生のトラウマになる恐れがあるので、今は宝の時のよしみで柵の内側までは出入りを許されている傍野としては、直接は関わってやれないのだ。
『もしも家の持ち主が代わる事でもあったら、その相手とも友誼を結んで信を得てもらわなければ、あなたに便宜は図れないと思われる。情報を埋め込めば融通は効くが脳に干渉をするので、宝に禁止されているのだ』と、まだ出入りが許されている頃に注意も受けている。
ちなみに外面がよくてこの家の前まで侵入を果たした男は、玄関で見えない圧力に押し戻され悪態をついたせいで緩い力ではあっても断固として柵の外まで押し出され、その日は不本意な顔で帰って行った。
さすがにそんな眉唾ものの出来事を周囲に言って胡散臭い目で見られるのは避けたらしいが、後日その事で宝本人を詰問しようとする場に居合わせた傍野の前で口を開いた途端に、「……なんだっけ?」といつもの温和そうな顔で首をかしげたのだった。
そんなわけで滞りなく家の引き継ぎを済ませたい傍野としては、できれば活気に溢れる玉生の友人たちと共に家と対面してほしいのだ。
正直、今日ここへ来たのもこの位置を玉生に覚えさせるのが目的で、もっと近道はあったがあえて近くの電車やバスの停車場を通って、利用に必要そうな情報を話題にして聞かせたりもしたのだから。
本人も今後の利便性を考えたのか――もしかしたら万が一自分で帰る必要になったらなどと心配したのかもしれないが、熱心に聞き入ろうとする意気込みはあったものの、その不安からかどうしても注意力が散漫になる様で残念ながらどれだけ頭に入ったかは怪しく見えた。
とにかく傍野としてはあえて重要な事を黙っているとも取れる自分が一緒では、玉生の友人たちになんらかの作為を疑われそうな気がするので、しばらくは必要以上に関わらないつもりでいる。
実際、過去に宝が自宅に招待した友人の中にはもとより頭が固くて冗談が通じない性格の者がいて、案の定と言うべきか自分をからかうための仕掛けを疑い腹を立てた。
そしてその後日、訪問の感想について首を挟んできた第三者との会話中に「家に仕掛けをして驚かすのは悪趣味」程度の事を口に出しかけたのを、次の瞬間には以前に押し掛けて来た人物の様にすっかりと忘れていたのだ。
「何か怒っていたでしょ?」と聞かれても「怒ってないが?」となんの疑問もなく不審そうにしていたぐらいだ。
今も宝についてある程度の事は把握しているが、家の事に関してはまったく記憶にはない様だ。
なので傍野としては痛くもない腹を探られる危険を冒すよりは、不思議は専門外ととぼけるべきだろうと判断したのである。
それよりはむしろ、進学などで住所が必要になるだろうと玉生に土地家屋を相続する手続きをしたところに、どこからか聞きつけて今さら宝の遺産に色気を出す薄情なその親族の排除に専念すべきだろう。
僅かながらも親の残した遺産と、引き取った子供の分の補助金を受け取ってもロクに姉弟に使わなかったのだから、受けた恩など差し引いても搾取が過ぎて多少の意趣返をしてもバチはあたるまいと遠慮はしないつもりだ。
件の頭の固い友人に頼めば、正義感が強くお堅い方面には顔が利くので上手く協力してもらえるだろう。
その件が片付く頃には、この家の事も落ち着いているといいと思っているのだが。
『そのためには、玉生が友人との会話で持ち出しやすい情報を多く話題にするべきか?』と傍野は気を揉む。
なんとなく玉生は、貰った物の話題を言い出すのを躊躇するタイプの様な気がするのだ。
そんなある意味絶妙のタイミングで、その微かな鳴き声は耳に届いた。
ぅなぁ〜ぉ
「……」
ぅなぁん
「……まだ少し余裕はあるんですが、後日に改めて、その――」
片手でも握り込めそうにガリガリなハチワレの子猫を、「念のために持って来てよかった」と斜め掛けにした鞄から取り出したタオルでくるんだ玉生は、辺りをキョロキョロと見回している。
「こんなにガリガリなのが一匹だけでいるなら、もう迎えは来ないものらしいぜ」
野良は弱った子供を連れては行かない、そういう話を耳にしたことがあるとの傍野の言葉に、もう鳴きもせずタオル越しの体温と僅かにムズがる動きでしかその生存もわからないような子猫に、玉生の眉が下がる。
柵の外に停車していた車まで歩きながら少し考え込んでいた玉生は、助手席に乗り込みながらその結論を口にした。
「『捨て猫をみつけたら、絶対に自分の所まで連れて来るように!』と普段から言っている友達にこの子を渡したら、すぐアルバイトの時間になると思うので、来週にでも出直して来ようと思います」
その友人は、今日も「用事がなければ付いて行くのに」と言ってくれていて、帰りに一度顔を出すようにと念を押されている。
多分、彼なら他のみんなも誘って一緒に見て回ろうと言い出しそうな気がするので、今後ここに住む事を考えるとむしろこちらからそれを頼んだ方がいいのかもしれないと思い、『相談してみよう』と玉生は結論を出した。
それに、心配していたよりも都心から離れていないので、「広い庭が自由になるなら、畑作って変わった野菜を育てて食べたい」と言っていた友人や、「最近うちの近所の空き地で工事はじまってさー、ちょっと身体動かすのにいい場所だったんだけどなー」とボヤいていた友人ならここで同居してくれるかもしれない。
「――改めて、友人を誘って探検してみます」
玉生が前向きな気持ちでその気になったのに傍野もホッとしたようで「おう。ちなみに電気は点くし水も流れるからすぐ生活できるんだぜ」と言って、来る時も案内した道の説明などを念のためにもう一度おさらいしてくれる。
玉生も行きは緊張から上の空状態で通った道に今ひとつの自信が持てなかったので、今度は注意して目印になりそうな物などに気を付けて車窓を見た。
流れる景色は自然に溢れ屋敷の周囲を覆い隠しているような印象すらあるが、不思議な程に閉鎖的といった負の感情にはつながらない。
そんな緑を抜け、アスファルトで舗装された車道へ出る前の砂利道で車を停止させた傍野が、窓を開けてからクイクイと親指で道の脇を示す。
玉生が身を乗り出して見ると、鉄のポールに付いた白地のプレートに赤で注意書きと大きな丸、その丸の中に白い横棒が一本というよく街で見かける標識と似たマークが記されていた。
「私有地の入り口はその進入禁止の標識が目印にもなるからな。で、向かいは蔵地バス停と郵便局、分かりやすいだろ?」
車ではこちらが近道になるからと、通りに出てから今度は路面電車の停留所を横切るのに「思ってたよりも近い?」と玉生は思わず呟いた。
「あの家からこの辺まで車で十分として、余裕を見て自転二輪で三倍弱、歩きで九倍弱くらいだろうな。バスはそっち行きの路線もあるけど、蔵地の街辺りは人気があるから混んでる時間に当たると大変みたいだぜ」
傍野の言葉に思い返してみれば、郵便局の向こう側はキレイに整備された通りが続く、いかにも開発された街の印象だった気がする。
自然の緑が壁になっている家側から見たら、道を横断しただけで街中に出られるが喧騒からは遮断された利便性のいい立地だと言えるだろう。
そうしているうちに気付いたら玉生も知っている場所に出ていて、そこからは近道を選んでくれたらしく目的地まではあっという間だった。
すぐそこが友人の家だと言うと、門の前で車を停車させてから、「おっと、忘れるとこだった」と傍野はキーケースにまとめられた家の鍵束を玉生に渡してきた。
それを鞄に慎重に仕舞ってからタオルごと子猫をそっと抱える玉生の動きを目で追いながら「困った事でも聞きたい事でも、何かあったら遠慮なく連絡よこすといいよ」と言い置いた傍野は、その内心で『敷地内に入れたって事は“あの家”も認めたって事だろうから、後はどうにでもなるだろ』と肩の荷を下ろした。
しかし、と玉生の背中を見送り、「あのちび猫は、ヤツの仕込みか?」と呟いて去って行ったのだった。
「あ、ここからだと移動でギリギリかも」
腕時計で時間を確認すると思っていたより余裕がないのに気付き、玉生は慌てて日尾野という表札のある門扉に取り付けられたインターホンを押す。
「おや、これは倉持様。お久しぶりでございます」
対応に出て来たのは日尾野の家の執事で、尾見というロマンスグレーの温和な紳士だ。
玉生も顔馴染みで随分と良くしてもらっている。
「こんにちは、尾見さん。あの、今は時間がなくて、また明日にでも出直して来ますので、この子を尚君に……っ」
「はい、承りました。それと本日は学園通りのミルクホールでお仕事でございますよね」
焦る玉生から子猫を包んだタオルを優しく受け取ると、尾見は直ぐ側でアイドリング状態の車の扉を開いた。
「寿尚坊ちゃまから、もしも時間がないと判断しましたら、そのままミルクホールまでお送りするようにと仰せつかっておりますので、どうぞご遠慮無く」
強引さを感じさせない手際で玉生を座席に押し込むと、運転手に「丁寧にお願いしますよ」と声をかけ「では明日。美味しいお八つなどをご用意して、お待ちしております」との言葉と共に静かに扉を閉じた。
慌てて振り返ると一度お辞儀をしてにこやかに見送ってくれるのに、玉生は所在なさ気に宙に浮かせた手と共に頭を下げた。
車で玉生も知らない近道を通って来たおかげもあって、思ったよりも余裕を持ってバイト先のある学園通りに到着した。
その玉生のバイト先であるミルクホールは、国の施設に店舗を構える代わりに社会貢献として孤児院から一定の人数を雇い入れているのだが、若者に人気のあるスポットなので当然ながらその競争率は高い。
玉生の場合は自炊の下地らしきものもあり、簡単なメニューなら作れて混雑時には厨房の方でも戦力になるのが採用の決め手となった。
そんな孤児組の一人によく遅刻して来る者がいる。
それにはちゃんとした理由があり、大遅刻とまではいかないのと仕事熱心で要領も客受けもよく、人手が足りない時などにシフトに入る事などで大目に見られているのだが、それが面白くないのか店員のうちに孤児を全員一緒くたにする人物がいるのだ。
玉生もバスの到着の遅れで遅刻してしまった時、彼女に「いい加減にして。親がいない人ってこれだから」とくどくど嫌味を言われてしまった。
ほかの店員が止めに入り気にしなくて大丈夫だと言ってもらえ、遅刻魔にも「とばっちりでごめんな〜」と謝られたが、それ以来やや神経質になってしまいバイト前になると5分ごとに時計を見る癖が付いてしまったのだ。
おかげでこの頃よく寿尚に、「俺も気を付けてやるから、少し落ち着け」と注意されたりもする。
今日もなかなか来ない玉生が、遅刻に気がいって焦っているだろうと予想して、車で送るように尾見に言ってくれたのではないだろうかと思われる。
自らを猫の従僕と名乗る猫好きの寿尚は、小学校入学時の初対面からずっと玉生を「たま」と呼んで可愛がっているのだ。
その頃は玉生はまだ孤児院に入ったばかりの頃で、ガリガリに痩せていたせいで大きくてギョロリとした目がよけいに子猫を思わされ、視線が合った時から寿尚にとっては「うちの子」なのである。
一学年下の玉生はずっと小柄な事もあり、年の離れた兄弟ばかりの末っ子で大人びた方へ成長した寿尚にとってはそれだけでも庇護し続ける理由になり、今も危なっかしい子猫的な保護対象であるらしい。
実際に今日もこうして気を回してくれたおかげで余裕を持って引き継ぎができ、いい雰囲気で仕事がはじめられる。
よく寿尚が同乗を勧めてくれるので、すっかり玉生とは顔見知りになった運転手も気の利いた人で、悪目立ちしない様に裏口から少し離れた場所で降ろしてにこやかに「お気を付けて」と声をかけてくれた。
ペコリと頭を下げてお礼を言う玉生が店の裏口から入るまで見届けてくれたのに、くすぐったい気持ちで給仕の制服に着替えて「倉持入りまーす」とカウンターに向かうと、「おお、倉持。参番に胡桃のミルク茶とミルクレープ、あとこのクリームソーダな」とさっそくの仕事だ。
「で、これ運んだら裏回ってキッチン手伝ってくれ。この時間、人手が足りないんだ」
今日は週末のせいか特に混んでいて、いいタイミングでバイトに入れたと車を出してくれた日尾野の家の人たちに何度目かわからない感謝をしながら、玉生はせっせと労働に励むのであった。
その後は賄いを作る暇も食べる暇もなく「今日は本当にご苦労だったね」と店主が一食分に色を付けた手当てを、安全のため院までまとまって帰る玉生たちに配ってくれたので、それぞれ帰り道で好きな物を買って食べた。
餡饅を半分取られ鯛焼きの半分をよこされながら、『明日、ちゃんと相談しよう』と前向きな気持ちになる玉生だった。