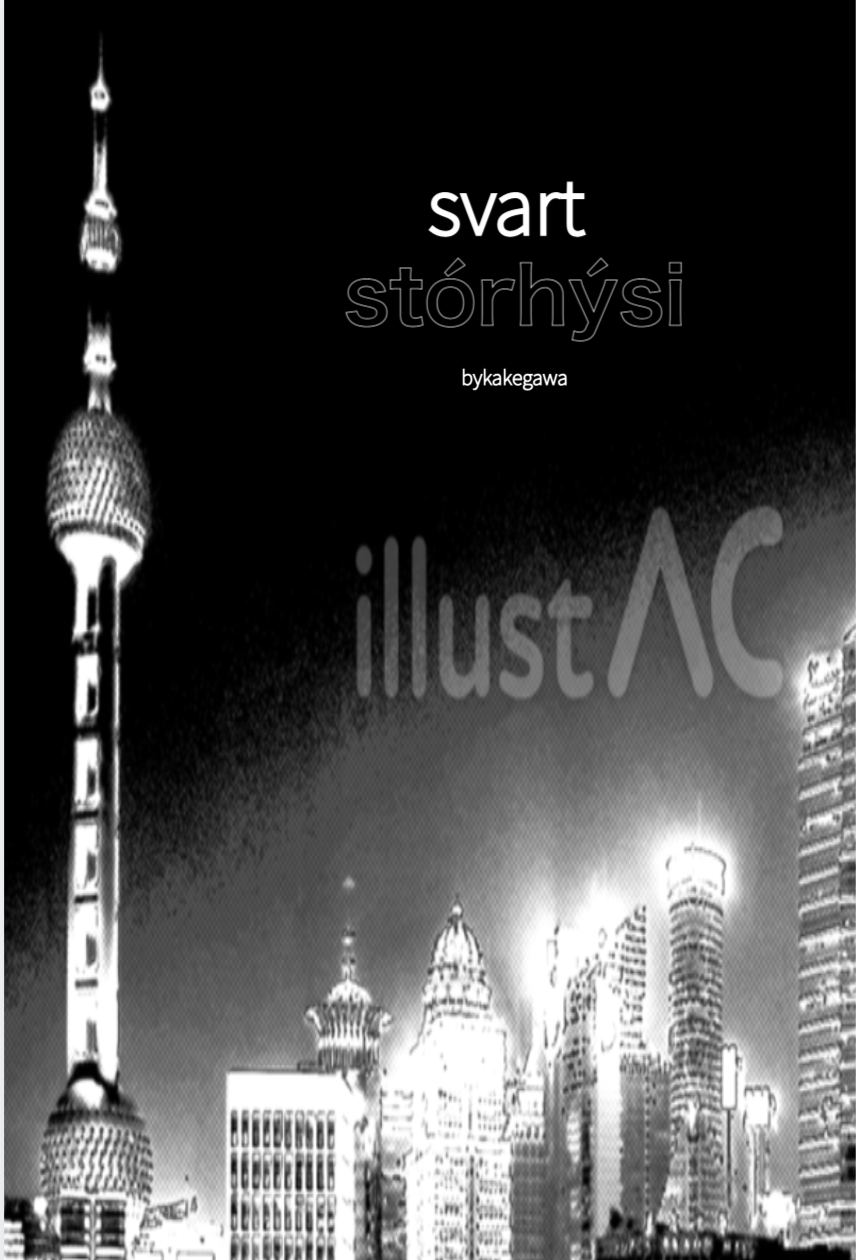其の四
太陽が一日の役目を果たし、山峰の稜線にその姿を消しかけていた時分。
緊急の軍議のために女王の本営に集められた四人の騎士団長たちは、そこでフランソワーズの口から思いもがけぬ言葉を聞かされた。
すなわち、今夜軍を動かして攻撃にうってでる、ということをである。
フランソワーズの「突飛な」言動や思考というものに、四人の騎士団長たちは耐性や免疫というものが十分備わっていたはずなのだが、そんな彼女たちでもとっさの反応に窮し、黙したまま困惑の視線を交わしあっていた。
ややあって小さく息を吐いたヒルデガルドが、一同を代表して声を発した。
「陛下のお決めになられたことに、私どもは身命を尽くすのみにございます。ただ、ご深慮の一端をお教えいただければ、私たちも迷いなく戦いに臨めるのですが……」
フランソワーズはうなずき、自らの作戦を語りだした。
フランソワーズの策――。
それは軍を二手に分けて湖畔を左右両側から攻めあがり、湖畔北側に陣を敷く同盟軍を挟み撃ちにしようという、いたってシンプルなものだった。
それだけに、かえって「粗」が見えやすかったのかもしれない。
四人の将軍たちはふたたび視線を交わすと、今度はペトランセルが疑問の声を発した。
「おそれながら陛下。兵力を二分しては、逆に敵の思うつぼにございませんか?」
ペトランセルの懸念は、およそ用兵の知識に皆無なランマルにもよくわかった。
女王軍の兵力二千に対して、同盟軍はおよそ三千。
ただでさえ兵力で劣っているというのに、その上軍勢を二分して挟撃戦をしかけたところで、敵は全軍をもって左右いずれかの半数になった方を攻めるであろう。
そうなれば挟み撃ちにする前に、こちらが各個撃破の憂き目にあうかもしれない。
その危険性をペトランセルは指摘したのである。
もっとも、その点について指摘されることはフランソワーズも予想していたようで、手にする紅茶のカップをテーブルにおくと穏やかな口調で応じた。
「そのとおりよ、ペティ。だから攻める際には、ちょっとしたトリックを用いるのよ」
「トリック……?」
戸惑った様子の四将軍に、どこか興がった口調でフランソワーズが説明を続けた。
先に話したように兵力を二手に分けるが、単純に半分に分けるのではなく、湖畔を右回りで攻めあがる右翼部隊はガブリエラのタイガー騎士団が一団でうけもち、左回りで攻める左翼部隊は残りの三騎士団が連合してうけもつ。
その際、タイガー騎士団は松明を一人が二本使用しながら進軍し、逆に三騎士団側は三人で一本の松明を掲げながら進軍する。
こうすることでタイガー騎士団を倍の兵力に見せ、逆に三騎士団側を三分の一の兵力に見せる。
月光のない暗夜にあっては遠眼鏡による視認も限られ、敵は松明の灯火が少ない三騎士団側を兵力が少ないと思いこみ、各個撃破すべく全軍をもって攻めこんでくるだろう。
三騎士団側に敵を誘い出し、タイガー騎士団が駆けつけてくるまでその場に釘付けにし、呼吸を合わせて敵軍を前後から挟撃する。
視野のきかない闇夜と松明の灯火を利用した、まさにトリック戦法であった。
「なるほど、トリックというのはこのことでしたか」
一様に得心したようにうなずく騎士団長たちに、フランソワーズは薄く笑ってみせた。
「松明の数を見れば、当然敵は左翼の三騎士団側を少数と思いこみ、まずそちらを潰してやろうと攻めてくるでしょう。トリックとも知らずにね」
低声の笑いを漏らしながらフランソワーズはガブリエラに視線を転じ、
「ガブリエラ。交戦を確認したら、そなたは得意の高速行軍をもって湖畔を急ぎ回りこみ、敵の背後を強襲しなさい。夜目が利くそなたであれば可能なはず。いいわね」
「かしこまりました、陛下」
ガブリエラが低頭して応じると、フランソワーズはさらに強い語調で断じた。
「いつまでもこんな所でグダグダしていられないわ。今夜中に奴らとは決着をつけて、一日も早く国都に向かうわよ!」
語尾に重なるようにランマルと四人の騎士団長たちは椅子から立ち上がり、いっせいに頭を垂れた。
かくしてその日の深夜。作戦は決行されたのである。
昨日まで地上を明るく照らしていた月と星の群は厚い雲に隠されて、今宵のウェミール湖一帯は濃い闇と深い静寂に包まれていた。
しかし夜半過ぎ、その闇と静寂は馬蹄のとどろきと兵士たちの気勢、そして、その手に掲げられた松明の灯火によってに破られた。
本営を進発した四騎士団が二手に分かれ、それぞれ湖の左右両岸沿いを進軍していったのである。
女王軍同様、昼夜を通して相手の動向を監視していた同盟軍がそれに気づかぬはずもなく、たちまち陣内に「夜襲だ!」「敵が動いたぞ!」という兵士たちの叫び声がとどろき、各所で緊急を告げる銅鑼が激しく打ち鳴らされた。
その異音に、自分の宿営内で熟睡していたクレメンス将軍はたちどころに目を覚まし、駆けつけてきた従卒の兵士に事情を求めた。
「な、何事だ、いったい!?」
「敵襲でございますぞ、閣下!」
「な、なに、敵襲!?」
兵士の一語に文字どおり跳びあがって仰天したクレメンス将軍は、泡をくった態で宿営から飛び出すと、湖の畔に立って遠眼鏡を覗きこんだ。
たしかに蛍の発光にも似た赤い光点の群が、湖畔を沿うようにして動いているのが見えた。
くわえて左右二手に分かれていることから、挟撃戦を仕掛けるつもりであることはクレメンス将軍にはすぐにわかった。
「お、おのれ、女狐め。夜襲とはこざかしい真似を!」
クレメンス将軍は憎々しげに吐き捨てたが、ふとあることに心づいた。
闇夜の中に揺らめく松明の数から判断するに、二手に分かれた軍勢の数があきらかにちがうのだ。
自分たちの方から見て湖畔を右回りで進んでくる軍勢のほうが、どう見ても松明の灯火がすくない。
同等の数をもって、呼吸を合わせて仕掛けるのが挟撃戦におけるセオリーなのだが……。
「妙だな、軍勢の数がちがうぞ。挟撃戦の仕掛け方を知らぬ女狐ではないはずだが……」
なまず髭を指先で撫でながらクレメンス将軍はつぶやいた。
女王を蛇蝎のごとく憎悪しているクレメンス将軍であったが、その用兵の才能だけは認めているのだ。
そのとき、幕僚の一人が出陣の準備ができたことを将軍に告げに来た。
この時点で用意が整っていなかったのは、いまだ寝着姿のクレメンス将軍だけである。
そのクレメンス将軍はこのとき判断に迷っていた。軍勢をどう動かすかに、である。
将軍の頭に真っ先に浮かんだのは、数の少ない方に全軍を進め、挟み撃ちされる前に各個撃破するという案である。
セオリー通りの用兵を好むクレメンス将軍らしいセオリー通りの案であったが、そのセオリー通りの命令を下すことをためらっていたのは、戦いのセオリーを無視している女王の存在である。
口惜しいことだが、あの女王が秀でた用兵家であることは認めざるをえない。
その女王がなんとも中途半端な挟撃戦を仕掛けてきたことが、クレメンス将軍にはどうにも解せなかったのだ。
あのバランスの欠いた軍勢の分け方には何か「裏」がある。【慎重居士】と称される将軍はそう結論づけた。
しかし、その「裏」がなんであるのかがさっぱりわからない。
遠眼鏡を覗きこみながら、ああでもないこうでもないと悩んでいる内にも、自身の幕僚たちが全員集まってきていた。
ややあって、いつまでも進軍の号令を出さないでいる将軍に業を煮やし、幕僚の一人が出陣をうながした。
「閣下、お下知を。全軍、いつでも出撃できますぞ」
「う、うむ、わかった」
と応えるも、あいかわらず遠眼鏡を覗きこみながら思案を続けている。
そんな将軍の姿にさすがに憮然となった幕僚らが、口々に苛立ちの声をはりあげた。
「閣下、早くお下知をお願いいたします!」
「何を迷うことがございますか。一方に全軍を進め、各個撃破すればよろしいではありませんか!」
「夜襲などというこざかしい真似をする女王軍に、目にものを見せてやりましょうぞ!」
どことなく非難調で口々に出陣をうながされて、ようやくクレメンス将軍は決断した。
従卒の兵に甲冑と武具をもってくるように命じると、周囲をとりかこむ幕僚に続けて命じた。
「よし、全軍をもって湖畔右側より攻めてくる敵軍勢を討つぞ。アルセコとパジェス両名に先鋒を命じる。私も用意ができしだいすぐに合流する!」