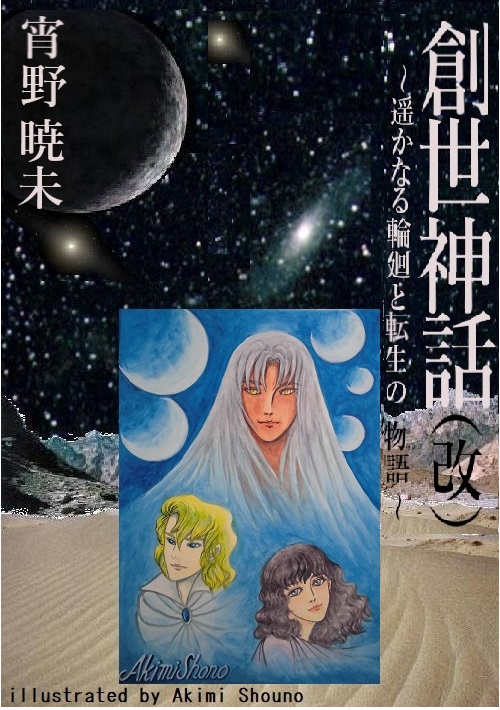第十五話
「全然リーズナブルじゃないわよ。神も人間もからだがあって心もある。どちらかひとつかけてもダメ。片方しかないなら、消えてしまうのは当たり前。それが死というものよ。意識だけ残されても、それは生きてるとは言わないわ。自分の手足、全身。からだがあればケガして痛かったりもするけど、それこそが生きてるという実感よ。歴史にどんなに名を残して、後世に語り継がれても、死んだ者は蘇ることはないのよ。アタシは正しい意味での生を選択するわ。」
「そうなんだね。からだも必要だなんて、なんて俗物なんだろう。弁ちゃん、は楡浬ちゃんをそんな風に育てた覚えはないけど。あっ、育児なんかしてないかな。ははは。でもそこまで言うなら覚悟を決めてよね。娘だからって容赦なんかしないよ。べ、別に代わりはいくらでも創造できるんだからねっ。ちょっとツンデレ入れちゃった。ツンデレ魔法美少女って、ミステリアス?しかし。」
弁財天は立ち上がってステッキを振り上げたような意識を楡浬にぶつけてきた。
「ああああ。」
楡浬は意識の中で、からだが十字架に張り付けられたという確実な感覚があった。その次に、瞬時に想像を絶する重量感ですべての細胞が押しつぶされたと感じた。同時に意識は途切れた。これが虚無というものなの?そう思考する暇は微塵もなかった。
「終末とは虚無感すら感じることができないものなんだ。楡浬はそう思った。・・・思った?アタシ、まだ意識があるの?」
「あん、あん、ああ~ん!」
弁財天が苦悶の表情で、三角帽子を噛んでいた。
楡浬の目に映像が映っていた。
「??アタシ、目が見えるの?いや、目があるわ。からだもある!」
大悟が弁財天をお姫様抱っこして、背中のツボを軽やかに押していた。
「楡浬の細胞が潰されていた時に、オレのからだに残っていた『楡浬の髪の毛』が反応したんだよ。それで目が覚めたのさ。」
「これが魔ッサージ!?世界一、宇宙一、いや時空一気持ちいいよ。138億年の疲れが癒されたよ、しかし。ガク。」
弁財天はだらしなく涎を垂らして果ててしまった。
「大悟!」「楡浬!」
ふたりは抱き合い、熱く唇を合わせた。すると、ふたりのからだは神宮久城から消えた。